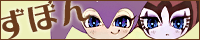 ずっと繋がってたい
ずっと繋がってたい|
ぬるい性描写あり 「ん…っ、はあ」 「…好き」 ナイツは自分の下で小さく震える筋張った身体をだきしめた。リアラはそれに応えるようにナイツの背に手をまわす。リアラの尖った爪が肩甲骨に食い込んでナイツの背に蚯蚓腫れをつくる。その痛みさえ甘い。熱に浮かされた身体には気持ちよかった。 リアラはナイツの肩口に顔をうずめて、呼吸と一緒に溢れ出しそうになるなにかを懸命に堪えていた。瞳は閉じられ、眉間に皺がよっている。彼の額から流れた汗の粒が重そうな睫に乗って、きらりと光った。 「堪えないで」 「ナイツ…もう…っ」 「大丈夫」 硬直したツノを先端から根元までなぞると、彼の身体が弓なりに反った。 「愛してる」 何度言ったかわからない。何度言っても足りない。ナイツは肩に縋るしっとりと濡れたリアラの頬を持ち上げた。リアラの唇の端はピッと切れて瘡蓋になっていた。ナイツはその傷を舌でなぞって彼の口を開けさせ、ゆっくり、深く口付けた。吐息を交換する。自己の中の何かが満たされる。 (数分前) ナイツはあてもなく夜のナイトピアの上空を飛行していた。眼下には雲の野が果てしなく広がり、右手に上るクリーム色の月の光が彼の頬を照らしていた。雲は切れ目なく広がっていて、終わりが見えなかった。この雲の野を越えたら、少しは世界が変わっていたらいい、とナイツは空を泳ぎながら考えた。 ふと自分の下に見慣れた影が見えた気がしてナイツは振り返った。自分とまったく同じ背丈、華奢な身体、ごつごつしたブーツ、二本の巻きぎみのツノ。ナイツはその場に停止した。するとそれもその場に停止したので、ナイツはそれが月光を切り取ってできた自身の影だと気づく。ナイツは目を伏せ、ため息をついた。 青白いトゥインクルダストを散らしてナイツは飛び続けた。空には何千もの星が煌いて眩しいぐらいだったが、ナイツの心は雲っていて、今にも雨が降り出しそうだった。 向こうの地平線できらりと光るものをみた気がした。どうせさっきと同じようにただの見間違いに違いない。ナイツは首をふった。 この雲の野を越えたら…となんとなく考えた自分をナイツは笑った。なんの努力もせずに、世界が都合のいいように変わることを願っている夢見がちな少女のようだ。 濃紺の空と綿毛の雲の間にぽつりと点が見え、それはどんどん迫ってきた。ナイツは紅く煌くトゥインクルダストの気配を感じて顔をあげた。彼のペルソナの漆黒の羽がきらりきらりと月光を受けている。 連れ戻しにきたのではないことは、彼の表情でわかった。 「リアラ!!」 ナイツは腕を伸ばしてリアラの胸に飛び込んだ。衝撃でリアラのペルソナが外れ、雲を突き抜けてはるか下方の海へ落ちていく。月は優しい光をふたりに投げかけていた。雲の上に切り取られたふたつの影がひとつに重なった。そしてそのままふたりは手を取り合って雲の野に舞い降りた。 (数時間前) ステンドグラスの吹き抜けの天井から差し込む光が大理石でできたホールの床に映って絵画を描いていた。 リアラはナイツに肩を掴まれて、冷たい大理石の柱に縫いつけられていた。彼の押さえつける力は、リアラにとってみれば簡単に振り払える程度のものだった。しかしいつも明るく能天気そうに見えたナイツが今見せている表情は真逆で、リアラは圧倒されて身動きが取れないでいた。 ナイツはリアラをきっと睨んだ。ナイツの大きな眼は涙をいっぱいためていて、今にも零れ落ちそうだった。 「なんでだよ!!リアラ、あんたは…」 ナイツの叫びは高い吹き抜けの天井に跳ね返ってわんわんとエコーした。ナイツはリアラの胸に額をつけてずるずるとくずおれた。 「オヤジはリアラのことなんかただの道具としか見てないんだ!道具、駒だよ…自分のナワバリを広げるためだけにお前を利用しているに過ぎないんだぜ?」 「わかってる」 「じゃあなんで…ッ」 ナイツは袖で涙をぬぐい、ぺたんと床に尻をついた。無機質で冷たい床にぽたぽたと雫が落ちて、ガラス玉のように転がった。リアラはしゃがみこんでナイツの頬に手を添えた。嗚咽を漏らして小刻みに震える背中を優しくなでてやる。 「私は私をこの世界に生み落としてくれたマスターに感謝している。だから、あの方の期待には精一杯の成果で応えたいんだ」 ナイツは何も言わず首を振るだけだった。 リアラは幼年期に戻ってしまったかのように駄々をこねるナイツの肩を抱きしめた。ナイツはリアラの腕の中でもぞもぞと身動きをし、顔を上げた。そしてリアラの肩の羽飾りを毟ろうとするかのように掴んでひっぱった。 「これも、これも、ペルソナと同じようにアイツからもらったモノだ」 ナイツはリアラをきっと睨んだ。ナイツの大きな眼は泣き腫らして赤くなっていた。ナイツはリアラのツノをぐいっと掴み、強引に顔を引き寄せて、青い唇に噛み付くように口付けた。 「オレはあんたにオヤジがあげられないものをいっぱいあげられるのに!」 「ナイツ!」 ナイツはリアラを突き飛ばして吹き抜けの天井を急上昇した。突き飛ばされたリアラの腰の防具が氷のように硬質な床にぶつかってやかましく音を立てた。直後、頭上からガシャアンとガラスが割れる音が、色とりどりのステンドグラスの欠片と共に、リアラの頭の上に降ってきた。 彼の涙色の星屑とともに残されたリアラは、床にしりもちをついたまま、きらきらひかる欠片を見つめてつぶやいた。 「悪夢に囚われるのは私だけでいいのに」 血の味が舌に滲む。リアラは傷を押さえて、指の先に付いた血液を見た。そこでリアラはナイツに口付けられたことに気づいた。その意味に気づいた彼は、自分の血の気のない頬がかあっと熱くなるのを感じて俯いた。 「…ナイツ」 (数日前) 呼び出されたリアラは主の前に跪き、視線を下にさげてにして命令を待っていた。いつもは神々しく背後で光っている主の光輪が、今は怒りに燃え、地獄の炎のようにめらめらと揺れていた。 「ナイツを監禁しなければいけない」 (数週間前) 「あそこは楽園だぜ、リアラ!オレたちの世界もあんなふうになればいいよな」 「とんでもない。ナイトピアは眩しすぎる。肌が焼けつく」 薄暗い書斎で、ふたりは埃っぽいふたりがけのソファに腰掛けていた。カーテンの隙間から差し込む光が、空気中の塵をきらきらと星屑のように光らせている。 「リアラは日傘でももっていけばいいや。ぶ…日傘とリアラ…ぶはっ」 「は?」 「つれてってやるよ!煌くせせらぎに天井のない澄んだ空、チョウのような羽をはためかせて合唱する住人たち」 ナイツはリアラの腕をつかんで引っ張った。リアラは相変わらず湿気てページの波打った本のページをめくりながら適当に返事をし、気のないそぶりを見せていた。けれど、ナイツが行こう、行こう、とせがんで、彼の身体を揺らすたびに、リアラはだんだん勉強するよりも、兄弟と光の下で遊ぶほうが、よりすばらしいように感じられてくるのだった。ナイツは最終的には彼が折れるのを知っていたから、何度も何度も紅い兄弟にまとわりついて、根気強く同伴を要求した。 「ね?ね?」 「…どの夢へ連れて行こうというんだ?」 (幼い頃) 「リアラ、すきー、あそんでー」 「うるさい」 「やだ、いっしょにいないとくるしーし。おとーさまはオレたちはついなんだって言ってた」 「つい?」 「さくらんぼみたいなモノだってジャックルが言ってた」 「つながってるってことか」 「よくわかんない」 (***) 「双生児か」 名づけを終えた創造主は手のひらの上で丸まっている紫と紅の小さな体を見て呟いた。彼らは創造主の生命力を限界まで注ぎこみ、凝縮した結晶だった。注ぎ込む際に溢れ出した力は玉座の周りを囲む石柱を破壊するほどだった。辺りは漆黒の闇に包まれ、創造主の光輪に照らされた靄がふわふわと足元をたゆたっているだけだった。 創造主はその体に対して小さすぎる玉座に腰を下ろした。靄を吹き飛ばすぐらい長々とため息をつき、二対の眼で手のひらを覗き込んだ。創造主の手のひらの上で、子供たちは互いの手をきつく握り合ってすうすうと寝息をたてていた。 創造主は二対の眼をオーロラのように怪しく色を変えながら、彼らを観察した。まだほころびがあるのか、片方の生命力が紅の炎となってふわっと溢れ出した。炎はあたりに広がって消えることはなく、創造主の目の前でもう片方の唇に吸い込まれた。創造主の眼が興味深げに見開かれた。 「意図していなかった…この子たちはお互いの中に大切なものを置き忘れている」 創造主は玉座にもたれて呟いた。 「不和を招かなければいいが」 手のひらの上で片方が寝返りをうち、もう片方の腹を枕にした。彼らは何も知らずにただただ夢を見ていた。 |
