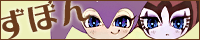 受け入れる
受け入れる|
リアラは自身の玉座に座りナイトメアの侵攻状況を確認していた。今期は順調のようで、彼の顔はほころんでいた。愛する主人の下へ報告にいきたくてしょうがないらしい。彼はてきぱきと事項をまとめ、席を立った。 「なにしてんの」 背後から声をかけられてリアラはバッと振り向いた。ビビットな玉座の影から紫色のツノが揺れている。ナイツがいつのまにかやってきていた。キャプチャーに捕らえておいたはずだったのに。彼はふがいなさに歯軋りをした。ナイツはなれなれしく肩に手を置いてくる。触れられた場所がじわりとしびれる。鬱陶しい。 「お前にかまけている暇などない」 肩の手を振り払う。彼は早く主人に報告したかった。ナイツはいつも何かとナイトピア侵攻の妨害をしてくるが、今回はうまくナイツの目を逃れてセカンドレベルを派遣できたのだ。褒めてくださるだろう。期待に膨らむ胸を押さえて彼は玉座を蹴って飛び立った。 ナイツは追いかけてくる。 「私に構うな。この場でキサマを拘束してやろうか」 「どうせワイズマンのところへいくんだろ?また怒られるだけなのに」 リアラの背に悪寒が走る。ナイツは唇の片側だけをあげて笑っていた。 「オレに隠れて新しいナイトピアを侵攻しようとしてたなんて知ってる」 鳥肌が立つ。リアラはナイツを正視できない。 「セカンドレベルは全部倒した」 「なに…」 「ワイズマンはカンカンなんじゃない?せっかく削った生命力が無駄になった。お前はまたやりなおしなんだ」 リアラはうまくいったと浮かれていた自分をなぐりつけたくなった。ファーストレベルの前ではセカンドレベルが何体居ても足りない。ナイツが自由になっているということは作戦失敗も同然なのだ。さっきナイツが現れた時点でやつを拘束し次の策を練るべきだった。主人の折檻が恐ろしい。彼は額に冷たい汗が流れるような気がした。 「ああそうやってワイズマンのことを考えているだろう」 ナイツは悲しそうに首を振る。リアラはナイツのオーバーなリアクションが気に障り、宙を蹴った。こいつは何を考えているのだろう。彼はナイツを睨んだ。こいつのせいで作戦は失敗続きで、主人の折檻はひどくなるばかりだ。 肩の傷跡を撫でられた。ナイツの細い指が紅い跡をなぞっている。癒えかけの傷に意識が向かう。リアラは居心地の悪さにみじろぎした。 「この傷は新しいな、ヘレンたちを助けたときのお仕置き?」 ナイツは俯いていてその表情は読めなかった。不愉快だ。 「お前は何故私の邪魔をするんだ」 ナイツは顔を上げなかった。黙っている。答えに迷っているのか、つま先が空中をさまよう。 しばらくのち、ナイツは答えた。目は合わなかった。 「リアラがワイズマンのことばかり考えているから…」 「……」 「お前の行動理由はどうしたらご主人様に頭をなでてもらえるか、だけじゃないか。オレを拘束するときでさえあいつのことを考えているんだ。オレがどんなにお前があいつに愛撫されるのを妨害したってお前はあいつのことしか頭に無いんだ。オレはそれが気に食わないんだ!オレはあいつを消し去りたい!お前がオレのことを考える余裕も作らせないあいつを!」 突然リアラは頭突きを食らって玉座まで飛ばされた。脳天に星が飛ぶ。彼が痛みをこらえて起き上がると額に硬いものがぶつかった。ナイツの顔に頭をぶつけたのだ。目の前で長い睫が重そうに瞬いた。息がかかるほど近かった。 口付けられるかと思ったリアラは反射的にまぶたを強く閉じた。だがナイツの息遣いは彼の唇を通り過ぎていく。 「あ…」 肩に鋭い痛みが走る。噛み付かれた。 「お前がこの傷を見るたびにオレを考えるようになるといい」 ナイツは同じ場所になんども歯を立てた。リアラの身体に主人の折檻とは違う痛みがじわじわと広がっていく。蝋燭で炙られるような表面的で乾いた痛みではなく、皮膚を貫き肉体の奥深くまでしみる痛みだ。 傷口から血液が滴って玉座を汚した。 自分の胸にひやりとしたものが落ちるのを感じてリアラは目を開けた。ナイツの頬を大粒の涙が伝っていた。無理して笑おうとして顔がゆがんでいる。 ナイツは濡れた頬を拭いもせずリアラの胸に顔をうずめた。 「好きなんだ」 その声はか細く震えていて、すぐ空気に溶け込んでしまった。 ナイツは自分を受け入れる余地のないリアラの心に余裕ができるのをいつまでも待つと言った。だがリアラはそんなことはできるはずがないと思う。主人は創造主だ。絶対の存在だ。主人以外のものを心にとどめておけるナイツのほうがおかしいのだ。しかしどこかでこのままずっと抱き合っていたいと考えている自分が居るのも否定できなかった。 ナイツのつけた傷が甘く疼いている。彼はこの感触は痛みのせいだとレッテルを貼った。そして泣きながら好きだ、待っているから、と繰り返すナイツの抱擁を甘んじて受け入れていた。 |
