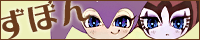 かまわないよ
かまわないよ|
どんなに求め合い繋がってひとつになろうとしても、それはかなえられない願いだとナイツはふと思った。“繋がること”と“ひとつになること”はまったく違うことなのだ。つめたい、けれどけだるい空気をまとった夜風が鼻先を掠めていく。ナイツはおぼろげに生まれる前の時間、創造主の胎内にいた時代の感覚を思い出していた。 そこには自己と他者の境界線などなかった。どこまでも自分であり、どこまでも他者だった。ナイツという名前もなく、彼は名前に縛られず自由に他者と五感を共有していた。彼は全てとひとつだった。 ナイツはリアラの太腿の上で寝返りをうった。 「おきたのか」 「……」 寝ていたわけではなかった。目を閉じていたのは、膝枕をされている状態で視線がかち合うと、頬に赤みがさしてしまうからだ。リアラの太腿は年頃の女子のようにふわふわと柔らかいわけではなく、むしろ締まって硬かった。しかしナイツにとっては至近距離で彼の息遣いを感じられ、ここちよく安心するものだった。 薄く紅が入った頬を見られたくなくて、ナイツは起き上がった。そして後ろからリアラを静かに抱きすくめる。このまま肌と肌が触れた場所から融けて交じってお互いの区別が無くなってしまえばいいのに。けれどもそんなことは起こるはずがなく、実際リアラは確かな感触をもってナイツの腕の中にいた。 「リアラ」 「ん」 「オレがワイズマンの足元をゆるがすようなことをしたら、お前はどうなる」 「…そんなことはさせない」 「もしもの話だぜ」 答えを聞かなくてもナイツにはわかっていた。創造主の意に添えなかったナイトメアンは彼の胎内に戻される。そしてそこであらゆる意識と交じり合いながら待機に入るのだ。 「ひとつになりたいよ、リアラ」 「……」 「一緒にあいつの中に戻ってくれる?」 青いルージュの唇がなにか言葉を形作ろうとして開いたが、言おうとした言葉は声にならなかった。彼はただぱくぱくと口を開閉しただけで、また真一文字に唇を引き結んでしまった。 うつむいたリアラの顔は月明かりの陰になってよく見えなかった。仮面のふちの黄金色ばかりがきらきらと輝いている。その顔を覗き込もうとナイツは身を乗り出したが、やんわりと肩に手が乗せられて押しとどめられてしまった。代わりにリアラはナイツの背中に手を回し抱き返してきた。おそるおそる指先が触れるぐらいの拙い抱擁。ナイツは彼の爪が背に食い込んで痛みを感じるほどに強く抱きしめてほしかった。しかしリアラは愛する主への後ろめたさからか、そこまではまだできないらしかった。 ひとつの泉からふたつの流れとしてふたりは生まれでた。上流へ戻ることができないのなら洪水を起こしてやる。ひとつになろう。なにもかも巻き込んでひとつになりたい。ふたりはお互いの肩に頭を乗せ、しばし体温を分かち合っていた。 |
