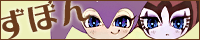 知るのが怖い
知るのが怖い|
オレたちはお互いの中にお互いを置き忘れていると、そうアイツが言ったことを覚えているか?オレとあんたはふたりで一人前なんだ、それはときどき格下のはずのセカンドレベルにいいようのない恐怖を感じることからもわかってると思うぜ、あんたは賢い、賢くてそしてバカだ。 あんたはほんとうは自由になりたいんじゃないのか?わざわざオレの牢獄をナイトピアに置かなくてもいいだろうに、そう仕向けたのはあんただ。おかげでオレは監禁される前とほとんど変わらない生活を送っているよ。ビジターもいるしな。 相変わらず私用では会いにこないあんたが憎い。近いうちにまた手紙を飛ばすよ。 手紙はリアラたちがよく使うクリーム色の羊皮紙ではなく、眩しすぎる真っ白な地に水色の罫線の入った紙だった。乱暴にノートを破いてつくった紙飛行機のかたちでそれは彼の手元にやってきた。破かれた端は繊維が飛び出していて、乾ききらないインクが合わさった面について汚くなっていた。 リアラは文面を眺めて、またか、と思った。歌うように語感のいい文章、繋がらない段落、自分に酔っているとしか思えない内容。ナイツは気まぐれにビジターが持ってきた紙になにごとかを書き付けてはリアラ宛に飛ばしていた。手紙の間隔から推測するに、ビジターは頻繁にやってくるらしく、ナイツは以前とほぼ変わらない生活を送っているようだ。 「ふん、むしろお友達と遊ぶ口実ができてよかったじゃあないか」 リアラは天井が見えないほど高さのある本棚の森の間を縫って飛びながら、紙飛行機の折り目がついたノートの切れ端を丁寧にのばした。朽ちかけた分厚い辞典の埃っぽい匂いが満ちているこの夢で、ナイツが送ってきた手紙だけが新しい風を孕んでいた。リアラはナイツの乱雑な筆跡に触り、インクが指につかないのを確認してから、半分に折りたたんで胸ポケットに入れた。返事は飛ばさない。けれど、鍵のかかった引き出しのなかにはこうしてナイツが飛ばしてきた紙飛行機が、すべてきれいに折りたたんでしまってあった。リアラは自嘲気味に笑った。 お目当ての本棚を見つけたリアラは、カビくさい棚の埃を払った。もうもうと煙がたち、リアラはごほごほと咳をしながら、そのなかの一冊に手をのばした。ワイン色の背表紙は金の箔押しがされてあったようだが、ところどころはがれかけており、ページは湿っていた。リアラは破かないようにそれを慎重に取り出した。リアラの肩幅ほどもあるその本は、長年放置された結果湿気を吸って重くなっていた。リアラはページとページがくっついてしまって読めないかもしれない、と思った。 リアラは本を胸に抱きかかえて、埃を舞い上がらせないようにそっとその夢を後にした。もう埃を吸うのはごめんだった。 リアラは自室にもどると、木製のどっしりとした書斎机に本を置いた。どさりと音がして、またもや埃がたった。リアラは顔をしかめた。 埃がおさまったのを見計らってから、リアラは使い込んで艶の出た革がピンと張ったソファに腰掛けて背もたれに寄りかかり、ふぅっとためていた息を吐き出した。部下が盆に載せて運んできたコーヒーを受け取る。一口啜って、焼け付くような熱さにリアラはすぐに舌をひっこめた。 「さて…」 ページをぱらぱらとめくる。中身は表紙の状態よりはるかに良かった。ページとページがくっついているところは何箇所かあったが、さして重要な内容でもなさそうだったので気にならなかった。ふと横をみるとさっきコーヒーを運んできた部下がまだそこにいて、リアラが開いたページを前かがみになって覗き込んでいた。細められた眼と口元だけがにやにや笑いをこらえながらぽっかりと浮かんでいる。 「ナイツさまがお送りになった手紙と何か関係がある書籍ですかね」 「………」 「そうですか、あのかたの文章にはなんの意味もない、ただ自分に酔っているだけだ、とよくおっしゃっていましたが」 リアラは何も言わずに手をしっしっと振り払う仕草をした。ジャックルは素直に従い、正面の扉から出て行った。リアラは自分にもよくわからない感情がもやもやと渦巻くのを感じて、そのまま本の上に突っ伏した。埃の匂いは気にならなかった。 本に突っ伏したまま、リアラは右手で鍵のかかった引き出しを探って錠を開け、新しい手紙をそこにしまいこんだ。 |
