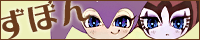 クレオパトラの真珠
クレオパトラの真珠|
巨大な硝子瓶の中。リアラが身じろぎするたびに、彼の四肢に絡まった鋼鉄の鎖が、硝子にぶつかり、冷たい音を立てる。鎖は硝子瓶の底の金具に繋がっており、彼を縫いつけていた。 ナイツは透明な壁越しに彼の瞳をみつめた。自重を支えるため、瓶の壁は分厚く設計されている。中の様子はいびつに屈折して見え、不安に駆られて視線をあちらこちらへ飛ばすリアラの輪郭もゆがんでいた。 硝子瓶には蓋がされていない。リアラは歯を食いしばり、入り口に戻ろうと全身の力を込めて鎖を引っ張る。しかし、力を入れれば入れるほど鎖は身体に食い込むだけで、びくともしなかった。 自由に空を駆ける者にとって、手足を拘束され地上に縛られることは、他のなによりも屈辱的なことだ。ナイツにはそれがよくわかる。 「どこにもいけないさ」 ああ、目の前に彼を留め置いておけることがとても嬉しい。リアラも自分を閉じ込めたときに同じように感じてくれていたのだろうか。 硝子のむこうできゅきゅ、と何かが擦れる音がした。彼の背中と硝子が立てた音だった。リアラは鎖を引きちぎろうとするのを諦めたらしい。力が抜け、壁にもたれるようにしてずるずるとくずおれる。 「ねえ、どんな気持ち」 「ナイツ、お前には経験があるくせに」 「ふふふ」 「出せといっても出さないのだろう」 「出さないね」 やっと縮められた二人の距離。ナイツは氷のように冷たい硝子ごしに彼の肩甲骨にキスした。リアラは振り向かない。当然である。分厚い硝子に阻まれ、なにも感じないのだ。声しか届かない。 彼との距離は10cmも無い。でもその10cmがとてつもない距離なのではないか。直に触れられないだけで、彼がもっと遠く感じられた気がする。ナイツはそんな考えを振り払うように首をふった。 「リアラ、もっと上を見て」 「…なんだあれは」 ナイツが指差した方向に、別の容器が浮かんでいた。透明な容器の中に液体が透けている。無色透明で水のようだった。容器は傾いており、いまにも内容物をリアラが入っている硝子瓶に注ぎだしそうな勢いだった。 その容器の位置を確認すると、ナイツはこれから起こることへの期待でわくわくしてきた。胸が高鳴り、言葉が喉元までせり上がる。自然と早口になる。この一言を聞いた彼の反応をはやく見たい。 「酸だよ」 弾かれたようにリアラがこちらを向いた。 「かの国の女王が真珠を酢の中に落として溶かしたように、リアラを飲み干してあげる」 ぱちん、指を鳴らす。容器が傾く。表面張力で辛うじて持ちこたえていた酸は、傾きに耐え切れず決壊した。 リアラが目を見開いて硝子の壁を叩いている。ナイツはもう一度硝子の壁に口付けた。 酸が硝子瓶に流れ込む。 「あああああああああッ」 酸はリアラの衣服を溶かし、鎧を溶かし、皮膚を焼いた。シュウシュウと煙が上がる。リアラの四肢が泡立ち、揺らいで、酸の中に霧散していく。生きながら溶かされていく苦痛に彼の眉間は深いしわが寄せられ、両目からは涙があふれていた。 ナイツは酸のなかに溶けていくリアラを眺めながら、涙を舐めとってやれないのは失敗だったな、と思った。どんなシロップよりも甘かっただろうに。もったいない。 それにしてもナイトメアンはとても綺麗に解けるものだ。醜く皮膚が引きつることはなく、まるでラムネ菓子が溶けるように泡だって解けていき、酸を紅く染めている。 「リアラ、とっても綺麗」 容赦なく酸はリアラを溶かしていく。 「…ナ…イ……」 「え?」 リアラはなにかを言いかけたが、そのとき酸が彼の喉を溶かした。首だけになったリアラと目が合う。彼の瞳からもう一筋涙が流れ、それを最後にゴボゴボと音を立ててリアラは酸に消えた。 真っ赤に染まった酸を湛えた硝子瓶を前に、ナイツはぺたんとしりを地面につけ、呆然としていた。やがてゆらりと立ち上がると、ナイツは硝子瓶の縁に脚をかけ、中に飛び込んでしまった。 |
