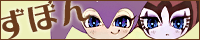 高鳴る世界
高鳴る世界|
リアラにとってナイツは不可解な存在だった。命じられたことはそつなくこなし、行動方針を固めて目標を達成しようとする彼に対して、ナイツは気まぐれに命令を曲解して捉え、たびたび主の頭を悩ませていた。この世に生を与えてくれた創造主を崇拝、敬愛し、主の力になろうと全力をつくすリアラは、主人をかえりみず自由奔放な行動をとるナイツを理解できなかった。双子は姿だけでなく好みや性格も似るというが、彼らはまったくその型にはまっていなかった。似ているどころか正反対といってもさしつかえなかった。 ナイツは都合のいいときだけ主の膝にすりより、要望が叶えられるとさっさとどこかへ飛んでいく。もちろん主人からナイツへの命令が正しく実行されることはめったになく、ナイツがほったらかしにした仕事は全てリアラに回ってきた。幼少の頃から確立されたこのパターンは、十分に主の片腕として働けるようになった今でも続いている。主の片腕として生み出された存在でありながら、ナイツはまったくその機能を果たしていなかった。 「く…」 なのに彼は主人に愛されている。リアラの奥歯がぎりりと軋む。主はなんだかんだと文句をいいながら、命令をこなさず、ただただ媚びるだけのナイツのおねだりに応えてしまう。陰でリアラが必死でナイツの分のノルマをこなしている間に、ナイツは何もせず主に頭を撫でてもらっていた。玉座の上で組んだ彼の華奢な膝関節が苛立ちを示すように揺れる。頭にかっと血が上り、彼は嫉妬している自分に気づいた。 自分も彼のように主に甘えればいいのだろうか。そんなことはできない。主のためには目の前の仕事をこなさなければいけないことは明白だし、彼のように主の膝にすりよる自分を想像しただけで恥ずかしさで身体が熱くなるのだ。 ナイツが時折自分にしかけてくる些細なちょっかいも困惑するものだった。ナイツは他人と触れ合うことが好きで、よくスキンシップをとろうとするのだが、そのようなことに慣れていないリアラは抱きつかれたり、触られたりするたびに心臓がばくばくと跳ね、その後に影響が出てしまう。まだそれだけならいいのだが、最近は純粋に仕事を妨害してくる回数が増え、ますますリアラを苛立たせていた。 だからリアラはナイツをキャプチャーに幽閉した。 リアラは監視のサードレベルに視覚を繋ぎ、ナイトピアの太陽の傾き具合を見た。いつもならそろそろナイツがやってきて、めちゃくちゃにひっかきまわしていく頃だと彼は思った。だがナイツはキャプチャーの中だ。そんなことはもうおこらない。せいせいする…。 しかし、この物足りなさは何なのだ。山積みの課題は邪魔も入らず着々と進んでいくのに、リアラの心には退屈さが募っていくだけだ。主にお褒めの言葉を賜っても、以前のような気分の高揚は得られなくなった。 「ナイツ」 思わず声に出してしまい、リアラはすぐさま口を押さえた。わたしは何を言っているんだ。ナイツが幽閉されるようにしむけたのは自分だ。それでいながらナイツがここに来ることを望んでいる?矛盾している。リアラは背をくの字に曲げ、心臓のあたりをぎゅっと掴んだ。意味のわからない感情が胸のうちで渦まいて、彼を苛む。 苦しい。苦しい。ナイツ。会いたい?会いたくない。こんな状態でまともに相手などできない。ああ、でも、この症状はどうしたらおさまるのだ。こめかみをつたう冷や汗が頬に流れ、その温度差にリアラはびくりとした。 わかっている。けれど、けして認められない。なんの努力もせずにかの人の寵愛を受け、独占するあいつが、こんなに…。 リアラははたと気づく。本当に自分が嫉妬しているのは誰だ? 目の端に青白い光の軌跡。 「どうしたんだ?リアラ」 つやつやと輝くキャンディカラーの紫色が玉座の目の前で浮かんでいた。ナイツは優雅に耳を揺らし首をかしげた。その目は膝の間に頭を埋めている彼を怪訝そうにみつめている。リアラはさっきまで不規則に速くなったり遅くなったりを繰り返していた心臓の鼓動が、その間隔を安定させていくのを感じた。 だが自分の顔が汗や涙でぐしゃぐしゃになっているのを承知していたので、リアラは顔を上げることもできず、そのままの体勢で硬直していた。 「キャプチャーは…」 「あんなの抜け出すのなんてわけないぜ。それより」 頬に滑らかな布の感触。 「顔をあげろよ」 ナイツはリアラの両頬に手をかけ強引に上を向かせた。流れたアイメイクが白い手袋の指先に汚れをつけてしまっていた。 息が近い。睫と睫が絡まりそうだ。サファイアの瞳にまじまじと凝視され、心のうちが見透かされてしまう気がする。こらえきれなくなりリアラは目を伏せた。そしてメイクが落ちた理由が「 」だなんて、ナイツが悟らないようにと誰ともなしに願った。 やはりリアラにとってナイツは不可解な存在だ。ナイツへの命令が正しく実行されることはめったになく、彼がほったらかしにした仕事は全てリアラに回ってくる。苦々しいと思う。それでもナイツと同じ空気を共有している時間は、他のどんな時間よりも安息を覚えるのだ。心臓がひっきりなしに跳ねていようと、だ。 しかし、それを認めてしまうとリアラの中で長く息づいていたものが変わっていってしまう気がして怖かった。わかっていても認められない歯がゆさを抱えて、リアラはまた苛まれることになりそうだ。 心臓の鼓動は緩やかな上り坂へ差し掛かった。リアラは膝の上に置いた手をぎゅっと握り、ナイツが次の行動を起こすのをじっと待っていた。 |
