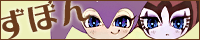 君の瞳が煌くから
君の瞳が煌くから|
大樹の枝葉は幾重にもおりかさなりヴェールをつくっていた。しかし太陽はそれを掻き分け掻き分けて地面にキスをおくる。まぶしい光がしっとりと苔の生えた地面を焼く。涼やかな風が吹く樹海の中に、小さな陽炎を作っている。 ナイツは雲に手を伸ばすかのように枝を茂らせた樹の、もっとも太い枝に横になってぼんやりとしていた。地表で踊る木漏れ日の激しさとは裏腹に、樹海はただただ静寂を湛えていた。鳥のさえずりばかりが、はるか、遠くのほうでやかましく聞こえているだけだった。 ナイツの頭上のはるか上に、ぽっかりと切り取られた空が見える。なんともなしにその窓を眺めていると、イモムシの形をした雲がいつのまにか飛行船に変わり、カナヅチに変化しー―――彼はふわあわあと大あくびをし、目の端をごしごしこすった。 …〜♪ 音が、笛の音が聞こえた気がしてナイツはふ、と意識をそちらに向けた。ふわりと起き上がる。ナイツは音のしたほうをしばし眺めていたが、森は相変わらず静かだった。 「鳥かな」 ぼそりと呟いて、ヤドリギの茂ったコブを枕にナイツは再び横になった。 …〜♪ …♪ ナイツは跳ね起きた。ナイツの青を湛えた瞳が木漏れ日を映して煌いている。彼があんまりにも勢いよく頭を上げたので、コブの近くにあった樹液溜りでティータイムを愉しんでいた蝶たちが、瑠璃色の翅をはためかせあわただしく四散していった。 蝶たちが見えなくなる前に彼は枝から飛び降り、音のした方角に勢いよく飛んでいった。あとに残された星屑は地面に降りる前に日光に焼かれて消えた。 訪れたことは一度もないというのに、樹海の真ん中のこのステージはどこか懐かしい感じがする。リアラはクイーンに主人からの新しい指示を渡し終え、仕事がひと段落したついでに、この場所へ立ち寄った。 扇形のステージを取り囲むように客席がひな壇上に並んでいる。そのすべてが鮮やかに濡れた翠色だった。木製のチェアには苔がびっしりと生えている。ふと見あげれば屋根にもツタが這っているらしく、舞台に緑色の天幕を降ろしていた。このナイトピアを生み出したビジターの、古い記憶が投影されているのだろうな、と彼は推察した。 リアラは腕の防具とグローブをはずし、舞台の端にきちんと並べて置いた。ぴったりとしたグローブに覆われていた皮膚が澄んだ森の空気を感じて心地よい。リアラは指を開いたり、閉じたりして、てのひらの体操をしながら、ステージの中央に立った。 …〜♪ …♪ 確かに金管楽器の、それもフルートの音色だ。ナイツははやる胸を抑えることも忘れて、樹海の中心に一直線に飛んだ。水気を含んだ涼しい風がナイツの頬を打った。メリーゴーラウンドで流れるような、楽しい、明るい曲調。どんどん近くなっていく音色を辿って、ナイツは飛んだ。ナイツの青を湛えた瞳が木漏れ日を映して煌いている。 森の中のステージ。彼のグローブをしていない素の手を見るのは本当に久しぶりだ、とナイツは思った。一面翠色の苔に覆われたこの場所に、不釣合いなほど紅い姿。 半径200m以内には誰もいないだろう。いつものようにリアラの目の前に飛び出していって、その腰に手を回してじゃれつこうか。そしてまたお前かと睨まれて、なのにまんざらでもなさそうなリアラの横顔にキスしようか。それも悪くないな、とナイツはふふっと笑った。 しかし、ナイツは観客席の後ろに静止した。今、出て行ったら彼はフルートを吹くのをやめてしまうだろう。もう少し、彼の音色を聴いていたかった。 長くとがった爪が楽器に引っかかりそうなのかもしれない。リアラの演奏はお世辞にも上手とは言えなかった。 あっ、間違えたな。半音はずした音色が誰もいない観客席に響くと、リアラはぴたりと吹くのをやめ、少し首を傾げてからまた数小節前に戻った。それを繰り返す。 ナイツの耳の奥のほうで、リアラの音色とシンクロするようにある曲が流れた。メリーゴーラウンドで流れていてもおかしくない、楽しくて、明るくて、けれど明るすぎて寂しさを感じさせる曲。自分が初めてつくったフルート用の曲だった。底抜けに明るくつくったつもりだったのに、どこか、隅のほうに陰が差してしまって、首を傾げた曲だった。ナイツはすぐに吹くのをやめてしまったのを憶えている。 憶えていたんだ。ナイツは呟いた。リアラの碧を湛えた瞳が木漏れ日を映して煌いている。 リアラが視えないフルートの上でぎこちなく躍らせる指は、しだいに滑らかな動きになっていった。さっき何回も間違えていた箇所も、いつのまにか繋がるようになっていた。 ついに一通り、きれいにとおし終わると、リアラはフルートを吹く手つきを解いた。視えないはずのフルートは、木漏れ日を反射して一瞬、金色に輝いた。そして彼は誰もいない観客席に向かってお辞儀をした。 ナイツは観客席の陰から飛び立って、蛍のようにひかるリボンをひらめかせながら拍手をした。リアラはぎょっとして固まる。 「その曲、憶えてたんだ」 「できたできた、と真っ先に私に聴かせにきた曲だな」 「そんなに何回も聴かせてないはずだぜ」 「…けれど、印象的だった」 ナイツはグローブをはめようとするリアラの手をとった。さっきまでフルートを操っていた、尖った爪に、筋ばった指。その手の甲に、ナイツはまるでジェントルマンのようにキスした。唇が生身の手の甲に触れた瞬間、リアラは驚いたらしくびくりと手を引いた。 「作曲者のオレがまたお手本を見せてやるよ」 見上げる。リアラの碧を湛えた瞳が木漏れ日を映して煌いている。幼い日のリアラの、ナイツが彼に一番最初に作った曲を披露したときの、驚きに目を見張る瞳が、ナイツの目の前で重なった。 リアラを客席の真ん中に座らせる。ナイツがステージに立つと、リアラは膝の上で拍手をした。初めてつくった曲を、初めて聴いてもらったあの日のように。木漏れ日を映す瞳。あの日も森の中だった。ナイツは視えない、銀色に輝くフルートをゆっくりと口元に持っていき、そっと命を吹きこんだ。 |
