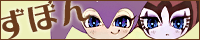 バレンタインデーのこと
バレンタインデーのこと|
チョコレートで少しかさばる鞄を抱えて帰ると、窓が開いたままの寝室にはすでに彼がベッドの上に我が物顔に陣取って娯楽番組に見入っていた。シーツの上には盛大に散乱した赤やらピンクやらの包装紙。あまりにも多いその量に唖然として挨拶もできないでいると、背後の気配に気づいたらしく彼が振り返る。 「ああこれ?リアラも食べるの手伝えよ。ここまでくると食いきれなくて腐っちゃうのがオチだぜ」 膝の上には破られたラッピングが丸められていくつか載っていた。ナイツはお菓子の山から適当にひとつ取り上げ、粉砂糖のかかったガトーショコラのようなものを私に渡そうとした。私は顔をしかめた。好意を軽く扱う態度が神経に障る。不安と希望が入り混じっているであろうものがこんな風に扱われては、いくらなんでも顔も知らない送り主に同情してしまう。ナイツはどれが誰からのものかなど覚えていないのだろう。胸の奥がぎゅっと掴まれたような。私はナイツの華奢な手を横に振り払った。 「こっちはこっちで手一杯だ」 「え?」 ふわふわのベッドに腰を落ち着けた彼の見上げる目がすこし見開かれる。視線がかち合い、ほんの一瞬の間があった。しまった、と思った。彼の目が細められ、視線が下がり、私が横抱きにしている鞄をじっと見た。ナイツはおそらく断りきれなかった私を叱るだろう。侮蔑と少しの嗜虐心を滲ませた声で、『オレというものがありながら本気のチョコレート断れないなんて浮気?自分の身の程をわかってないみたいじゃん?』 「あ…」 彼の次の言葉を想像し、無意識のうちに私は口元を押さえた。そのとき、ナイツはパッと満面の笑みを弾けさせ、ベッド横に立っていた私の腰をひっつかみ、シーツになぎ倒した。 「リアラももらったのか!どんなだ?見せてみろよ!」 ナイツは面白くて仕方がないという風に、固まっている私の抱えている鞄を奪ってジッパーを開けた。私は予期していたものとまったく違う彼の雰囲気に拍子抜けしてしまっていた。彼は私がバレンタインのプレゼントをもらったことが心底面白いらしい。笑いながら鞄の中から包みを取り出しては枕のほうに投げを繰り返す。 何なのだろう、ナイツは私が本気の贈り物を受け取っていても平気なのだろうか。自室に帰ってきたとき、彼宛ての贈り物の山を見たときと同じような息苦しさがまた戻ってきた。 「ひー、ふー、みー」 「ばっばか、やめ」 「ま、オレとは比べものになんねけど、リアラもそこそこモテんのな。ホワイトデー大変じゃん」 彼は自分のことを棚上げにしている。 「お前のほうが大変だろうが」 「オレはオカエシしないから大丈夫。でもリアラは無下にできないだろーこんなの。モテ男!」 唐突に私は大切なことを思い出した。鞄の奥のほう、教科書で埋もれたその下に、まだナイツが取り上げてない小さな包みがある。前日に焼いておいたココア味のクッキー。ナイツに渡すつもりだった。しかし、どうみても彼は私宛のプレゼントを用意している様子ではないし、また私はナイツが受け取ったプレゼントの予想外の多さとそれに対する彼の態度で、すっかり渡す気をなくしていた。今更こんな“手作り”の、ちゃちな可愛らしいちっぽけな贈り物をしたところで恥にしかならない。 「も、いいから…っ返せ!」 「やーだーぜー!」 ナイツは自分に圧し掛かって鞄を奪還しようと手を伸ばす私にキャッキャと嬌声をあげ、奪われまいときつく抱きしめた。そして私の鞄からまた包みを取り出し、「5個めー!」と高らかに宣言しながら私の下でそれを振り上げた。シアンと銀色の光がきらめくリボンがかかった、瑠璃色に包まれた小さな箱。私は息を飲んだ。手を伸ばすが届かない。いま、それは彼の手によって枕元に追いやられた贈り物と一緒くたにされるのだろう。頭のおくが、カッと白熱したむなしさか悲しみか何かで照らされて、私は何も考えられなくなった。ただその小包がベッドのヘッドボードに叩きつけられる、木と紙がぶつかるパコンという軽い音を、しかし重い音を覚悟して、私は身を硬くしていた。 「ねえリアラ」 突然、私の緊張はナイツの穏やかな声で断ち切られた。短いため息を吐いて、私は糸が切れた操り人形のように彼の薄い胸の上でうつぶせに脱力した。心臓が全力で飛行した後のように早鐘を打っている。瞼を下ろしておとなしくしていると、ナイツは私を両腕で抱え、私の頭においた手のひらの中で何かをもてあそびはじめた。 「この青い包みってさあ…ラッピングかわいくないし…男子からもらったのか?」 答えられなかった。私は彼がその包みだけを投げ捨てずに保持していることに驚いていて言葉が出なかった。私が黙っていると、彼はくっくっと笑って私の頭に軽くくちびるを押し当てた。私は目を見開いた。 「…ってか…これってリアラがオレにくれるやつだろ?」 私は跳ね起きてナイツの目を見つめた。ナイツはいつもと同じ不敵な笑みを浮かべている。 「なっ…な、違っ…!」 「違わない」 「…何故そういいきれる?」 「この包み、リアラの匂いする…ってのは嘘で」 ナイツは目を細めて私の顔を指差し、リンゴみたいになってる、と笑った。そういえば頬がとても熱を持っているのを感じる。 「お前わかりやすすぎ!」 そしてナイツは星屑色のリボンをまとったその小箱にいとおしそうにキスをし、もう一度私をベッドに埋め、優しく抱きしめてくれた。 「オレは、リアラからもらうもの以外は、どうでもいいの」 アンタだってそうだろ、とナイツは断定し、私はさらに眉間のしわを深くし、彼はまた笑った。 彼は悪質だと思う。彼は少女のようにめまぐるしく、可憐で、たおやかで、気まぐれなくせに、そうしたいと思ったらすぐに獲物を捕らえられる捕食者なのだ。そして学習能力のない標的は同じ手に何度でも罠にかかるのだ。私の腰に腕を巻き付け、彼はその柔らかな頬を私の胸に擦り寄せてこちらを上目遣いに見た。 「ね?」 今回も私は負けた。彼は私の沈黙を肯定とみなしたらしく満足そうに微笑んで、チョコレートの香りが残るくちびるを私のそれに重ねた。 |
